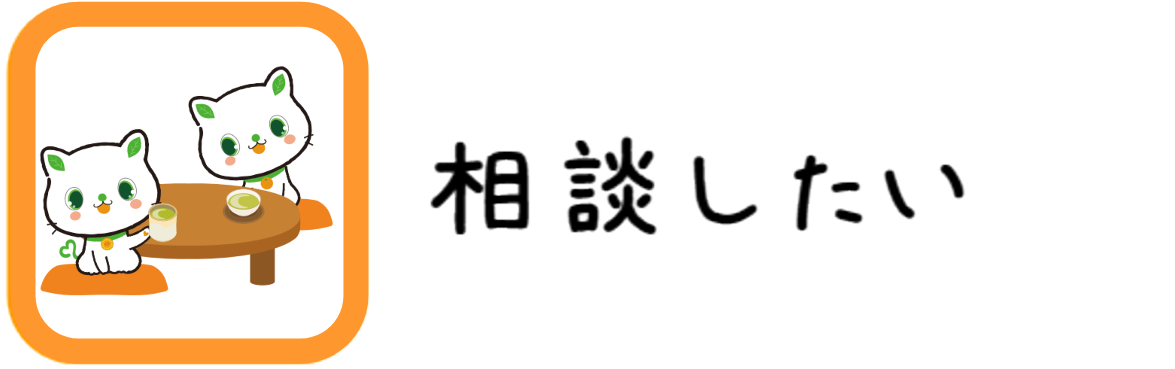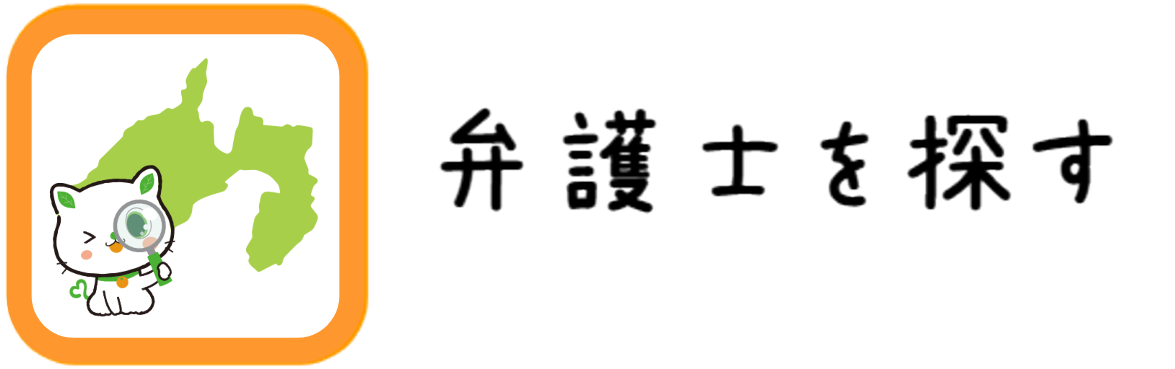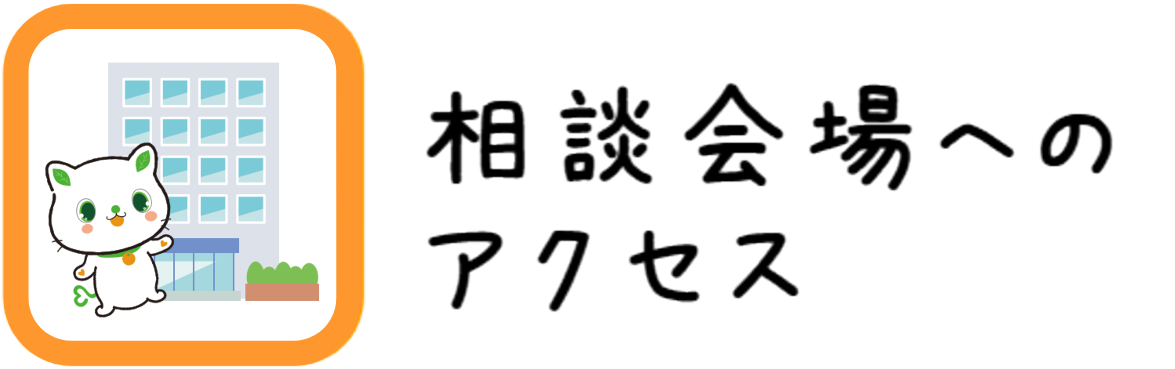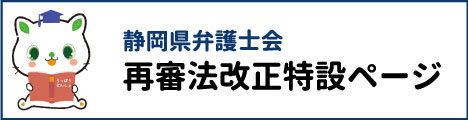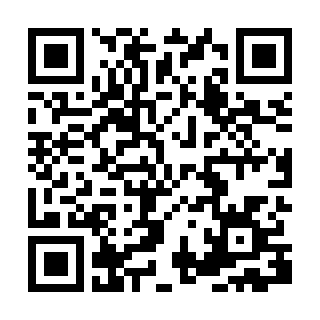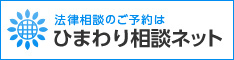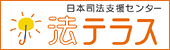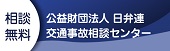1 昨年、袴田事件で再審無罪判決が確定し、福井女子中学生殺人事件でも再審開始決定が確定した。しかし、ここに至るまでには気の遠くなるような時間がかかった。袴田事件では逮捕から58年、福井女子中学生殺人事件では逮捕から37年である。
また、ここ静岡県で発生し、1989年に無罪が確定した島田死刑再審事件でも、赤堀さんの逮捕から無罪確定まで34年余がかかっている。
そして、上記事件以外にも、えん罪を晴らすために長年にわたって闘っているえん罪被害者やその家族は全国各地にいる。しかし、えん罪を晴らすために、余りにも長い時間がかかっているために、えん罪被害者やその家族の高齢化は深刻な状態にあり、えん罪を晴らすことができないまま無念の死を遂げたえん罪被害者も少なくない。もはや再審法(刑事訴訟法第4編)の改正には一刻の猶予もなく、再審法改正を「速やかに」実現することが何よりも重要である。
2 さらに、再審法の改正は、あくまでも、えん罪被害者の速やかな救済に資する内容でなければならない。
第1に、証拠開示を制度化しなければならない。再審が開始され無罪となった事例の多くでは、再審手続の中で新たに開示された証拠が重要な役割を果たしているが、それらの証拠のほとんどは警察官や検察官が所持している。ところが、現行法には証拠開示に関する規定がないため、無罪の根拠になりうる証拠であっても、それが開示されるか否かは検察官の裁量次第であり、また、裁判所による証拠開示の命令や勧告がされるか否かも、担当裁判官の姿勢次第である。また、裁判所が証拠開示の命令や勧告を行った場合であっても、現行法では、検察官がこれに応じるという保障もない。証拠開示の制度化は、今や急務である。
第2に、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止するものでなければならない。再審開始決定に不服申立てが認められているため、再審手続が長期化し、えん罪被害者の速やかな救済が妨げられている。袴田事件でも、再審開始決定に対して検察官から不服申立てがなされ、再審開始決定が確定するまでに10年近い歳月が費やされた。検察官に再審開始決定に対する不服申立てを認めなくても、検察官には、再審が開始された後の再審公判において確定判決の正当性を主張する機会が保障されているのだから、何ら不都合はない。
第3に、再審手続を明確化する改正でなければならない。えん罪被害者の唯一の救済手段である再審手続は、請求人にとって適正手続を保障するものでなければならない。しかし、現行法は、再審手続に関する規定はほとんどなく、いつどのような手続が行われるべきかも明示されていないため、裁判官の姿勢次第で審理の進め方がばらばらとなっており、いわゆる再審格差が生じている。このような状況を是正し、えん罪被害者に適正手続が十分に保障されるように、再審手続を明確化する必要がある。
第4に、証拠の保管・保存のルールを明確にする必要がある。現状は、捜査記録や証拠物の保管・保存のルールが不十分で、無罪を示す証拠が廃棄される危険性もある。
3 ところで、法務省は本年2月にも再審法改正を法制審議会に諮問する方針であるとの報道がなされている。しかし、
第1に、法制審議会に諮問し、法制審議会で議論するとなると、数年単位の時間がかかることは必至である。再審法改正のうち、再審請求審における証拠開示に関しては、2016年改正刑訴法の附則第9条第3項において、「政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示……について検討を行うものとする。」と定められているが、それから8年以上が経過しているにもかかわらず、政府における検討は全く進んでいない。したがって、法制審議会への諮問は今もえん罪を晴らすために懸命に闘っているえん罪被害者を「速やかに」救済することにならない。
第2に、法制審議会の刑事法関連部会の事務局は法務省刑事局が務めており、委員の人選も行っているが、法務省刑事局の主な構成員は検察官である。そのため、法制審議会の刑事法関連部会の審議は、必ずしも公正中立さが担保されるとは限らず、検察官寄りの結論とされることが強く危惧されると言わざるを得ない。そして、再審における証拠開示を頑なに拒み、再審開始決定に対する不服申立てを繰り返して再審開始に抵抗するなど、えん罪被害者の速やかな救済を妨げてきたのは、他ならぬ検察官である。このような検察官が事務局を務める法制審議会の刑事法関連部会に多くのことを期待することはできず、法制審議会における審議の過程において、改正法の内容が骨抜きにされ、「えん罪被害者の速やかな救済に資するもの」とならないおそれが高い。
法制審議会新時代の刑事司法特別部会の委員を務めた経験のある映画監督の周防正行氏は、西日本新聞に対して「法務省が法改正をつぶしにきた危機感を強くした」、「法制審が改革先送りのための組織体であることは、体験した私がよく知っている」などとコメントを寄せており、再審法改正を法制審議会に諮問することの危険性を明らかにしている。実際、この間の刑事立法を見ても、捜査機関の権限拡大に関する法改正は短期間で実現する一方、被疑者・被告人の権利拡大に関する法改正は遅々として進まない実情にある。
したがって、当会は、再審法改正を法制審議会の議論に委ねることに断固反対する。
4 自民党麻生太郎副総裁を最高顧問、各党代表を顧問(いずれも当時)とする超党派のえん罪被害者のための再審法改正を実現する議員連盟(いわゆる再審議連)が昨年3月に発足したが、発足から1年も経たない昨年12月下旬には、その加入国会議員数は360名以上と全国会議員の過半数を超えて今も増加している。そして、再審議連は、今通常国会において、議員立法による法改正を目指していると報道されている。
当会は、こうした動きを歓迎し、国会に対して、議員立法により速やかにかつ上記2の内容を含む適切な内容の再審法改正の実現を切に求めるものである。
静岡県弁護士会
会長 梅田 欣一
印刷用PDFはこちら


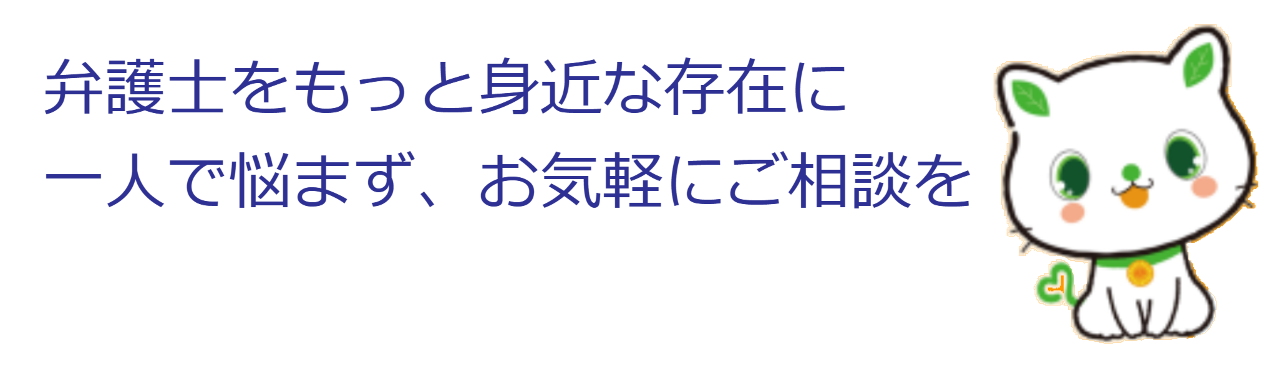
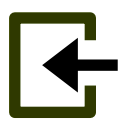 会員専用
会員専用
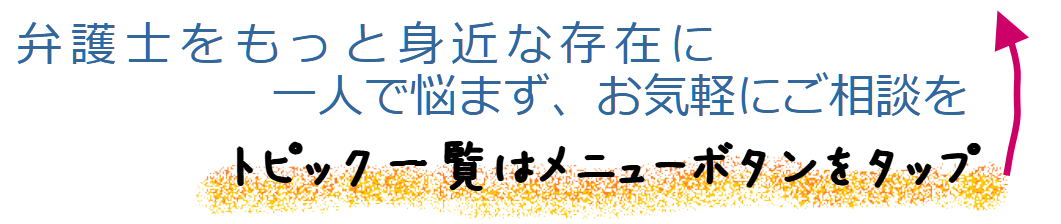

 ツイッター
ツイッター