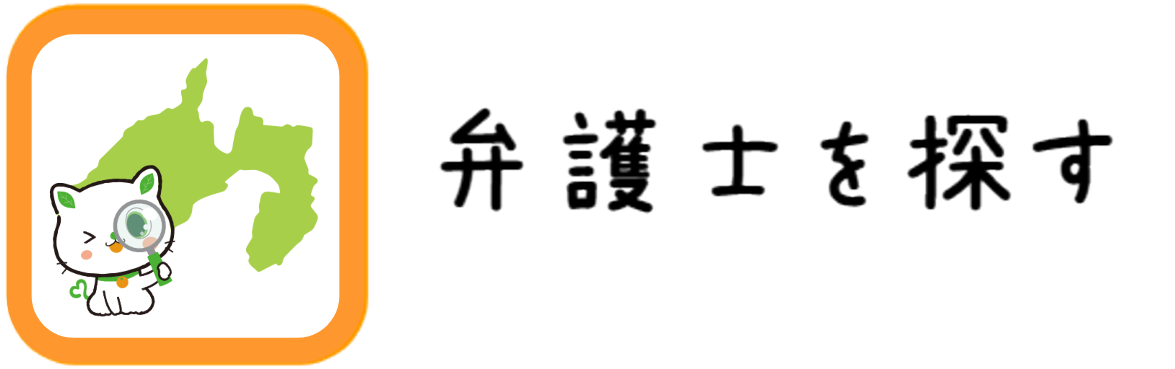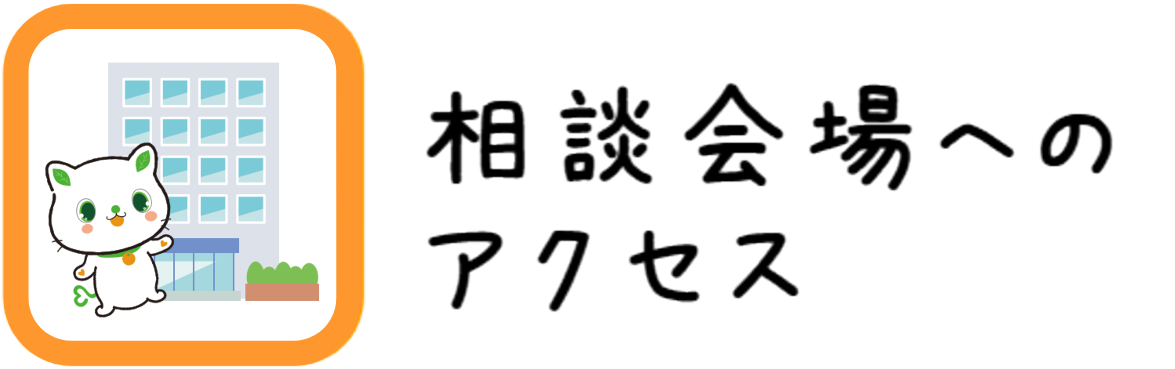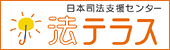- 当会は,2015年(平成27年)7月24日に少年法の適用対象年齢を引き下げることに反対する会長声明を発しているが,現在,法務省の法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会において,少年法の適用対象年齢を現行の20歳未満から18歳未満に引き下げることの是非を審議しており,遠くない時期に答申が出される可能性も指摘されていることから,この機に改めて本会長声明を発するものである。
- 法制審議会における少年法の適用対象年齢の引き下げの是非に関するこれまでの審議の結果,現行少年法が18歳及び19歳の少年の健全な育成と更生を図る上において有効に機能していることについては,共通の認識となっているものと解される。しかし,一方で,民法の成年年齢を18歳に引き下げる法律が成立したことから,民法の成年年齢と少年法の適用対象年齢が異なることは法的な整合性という観点から問題があるのではないかという指摘もなされている。
- 当会としては,民法の成年年齢を18歳に引き下げること自体に反対をする会長声明を2017年(平成29年)8月30日に発していたところであるが,民法の成年年齢が18歳に引き下げられたとしても,そのことを理由として少年法の適用対象年齢を18歳未満に引き下げなければならないものではない。
すなわち,法律における年齢区分は,それぞれの法律の立法目的や保護法益によって定められるものであり,民法の成年年齢から他の法規範の適用対象年齢が一律に定められるべきものではない。このことは,婚姻可能年齢(改正民法施行前男性18歳,女性16歳,改正民法施行後男女18歳),喫煙・飲酒可能年齢(20歳),被選挙権年齢(衆議院25歳,参議院30歳)といったように,法規範ごとに適用対象年齢が異なっていることを見ても明らかである。
そして,民法の成年年齢と少年法の適用対象年齢の関係についても,戦前の旧少年法(大正11年制定)においては適用対象年齢を18歳未満と定めており,民法上の成年年齢(20歳)とは一致していなかったことを見ても両者が必ずしも一致しなければならない性質のものではないことが分かる。なお,その後,少年法の適用対象年齢が20歳未満に引き上げられたが,それはむしろ,昭和23年の現行少年法制定時に,若年犯罪者の増加と悪質化が顕著になっている状況を踏まえ,その対応策としては刑罰を科すよりも保護処分に付する方が適切である等の理由からその適用年齢が20歳未満に引き上げられたものであって,民法上の成年年齢と合致させるべきであるとの理由によるものではなかったのである。 - 少年法の適用対象年齢を引き下げるか否かという問題は,少年の健全な育成と更生を図るという少年法の目的を達成する上で適用対象年齢を引き下げることが有効か否かという観点から検討されるべき問題である。
そして,現行少年法は18歳及び19歳の少年の健全な育成と更生を図る上において極めて有効に機能しているということができる。
すなわち,現行少年法は,すべての事件を家庭裁判所に送致し(全件送致主義),家庭裁判所調査官や少年鑑別所による科学的な調査と鑑別の結果を踏まえ,少年に相応しい処遇を決する手続を採用している。非行少年たちは,18歳・19歳も含め,多くが生育環境や資質・能力にハンディを抱えている。そのような少年たちが更生し,社会に適応して自立していくためには,現行少年法のきめ細やかな福祉的・教育的な手続と処遇が必要であり,かつ有効であって,国の重要な施策である少年の社会復帰や再犯防止につながっている。
そして,平成29年犯罪白書によれば,少年による刑法犯の検挙人員は昭和58年の31万7438人をピークに減少傾向となり,平成15年以降は一度も増加することなく毎年減少を続けている。平成28年は戦後最少の5万6712人(前年比14.0%減)であった(同白書3-1-1-1)。成人と少年を合わせた刑法犯検挙人員における少年の割合も低下し,また,少年による凶悪犯罪(殺人・強盗・放火・強姦の4罪名)の検挙人員も減少している。このように,少年事件が増加・凶悪化しているといった事実はなく,凶悪事件を含む少年非行事件の件数は減少傾向にあり,現行少年法は有効に機能しており,今これを見直さなければならない理由は存在しない。
むしろ,18歳及び19歳の者が少年法上の処遇から除外されることによって更生をする機会が失われて再犯のリスクが高まることが容易に予想される。すなわち,現在の少年被疑者全体のうち約4割もの少年が少年司法手続から排除され,それら事件の多くは,検察官による不起訴処分や略式命令による罰金刑により手続が終了することになりかねない。そうなれば,年齢引下げによって成人とされた18歳,19歳の若年者が立ち直りに向けた十分な処遇を受けられないまま放置されることとなり,少年が再犯に及ぶリスクを増加させ,ひいては,新たな犯罪被害者を生み出してしまうおそれも否定できないのである。 - こうした議論の状況を踏まえて,法制審議会では,あくまで18歳及び19歳の者を少年法上の処遇から除外することを前提としながら,家庭裁判所調査官の関与に代えて少年鑑別所・保護観察所の調査調整機能を活用することや,刑務所において少年院的な処遇を実施することを採り入れること、検察官が不起訴とした場合は家庭裁判所に送致して少年法と類似の手続を経て「新たな処分」を決定する制度などを検討しているとされる。
しかしながら,少年法の「健全育成」という目的に基づかない少年鑑別所・保護観察所の調査調整は,現在有効に機能している家庭裁判所調査官の調査調整機能に代わり得るものではない。また,刑務所は,主として懲罰としての刑務作業を課す機関であって,更生のための専門的な処遇を集中的に行える環境にないし,少年院的な処遇であれば少年院において行えば良いはずである。さらに,「新たな処分」制度には,少年鑑別所や少年院に収容する案と収容を伴わない案の2通りが検討されているとされるが,前者については,少年法が適用されないとする以上,処分の重さは行為責任の範囲を超えてはならないところ, 罰金や拘留よりも軽い処分である不起訴処分を受けた者に対して,なぜ施設収容をすることができるのかという法理論上の重大な問題があるし,後者の施設収容を予定しない少年審判類似の制度においては,処遇の選択肢が限定されることとなり,有効な効果が期待できない。
したがって,検討されているこれらの制度の実効性,合理性には大きな疑問がある。 - 他方において,18歳及び19歳の者を少年法上の処遇から除外することによって,これらの者の大人としての自覚を促し,その結果としてこれらの者の健全な育成と犯罪の抑止が図られるとする意見も見られる。
しかし,現行少年法においても,故意の犯罪により人を死亡させた重大事件については,原則として裁判員裁判を経て刑事罰を科すものとされ,平成26年には,少年に適用される刑の上限を引き上げる法改正もなされたばかりである。
このように,現行少年法を前提としても,少年に対し,その犯した罪に応じた刑事罰を科すことは十分に可能なのであって,上記法改正の効果について然るべき検証もなされないままに少年法の適用対象年齢を引き下げることは,立法事実を欠くものであって適切でないと言わざるを得ない。 - よって,当会は,少年法の適用対象年齢を18歳未満に引き下げることに改めて反対するものである。
以上
2019年(平成31年)1月24日
静岡県弁護士会
会長 大多和 暁
静岡県弁護士会
会長 大多和 暁


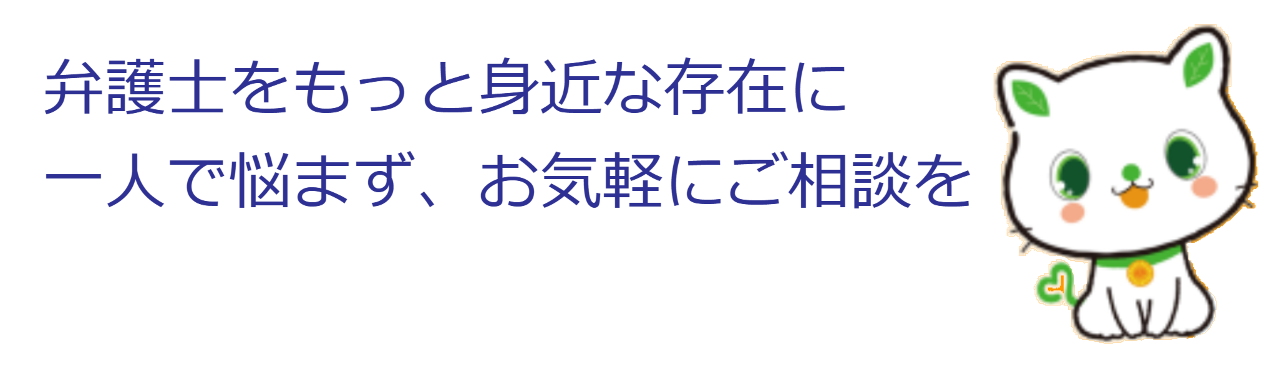
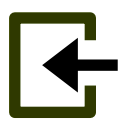 会員専用
会員専用
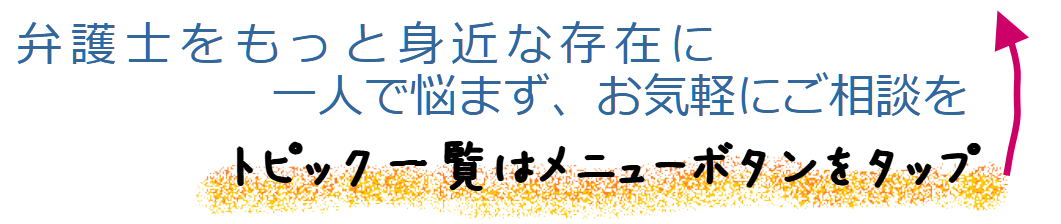

 ツイッター
ツイッター