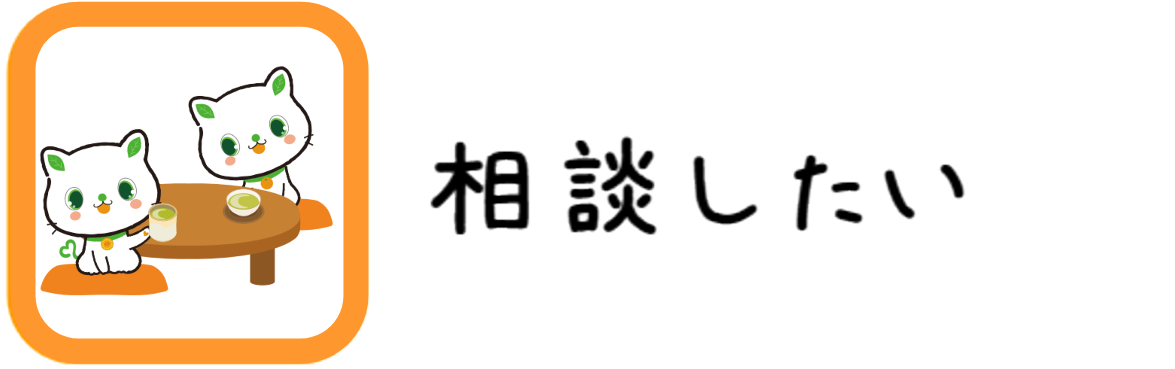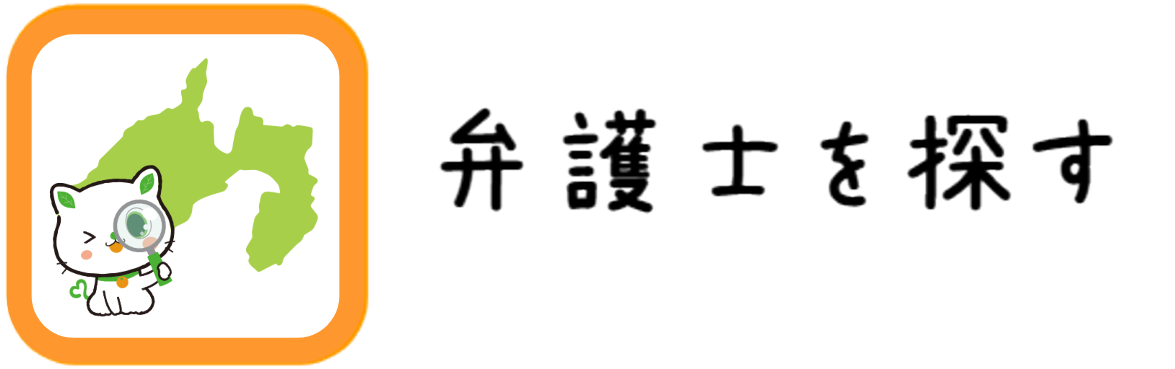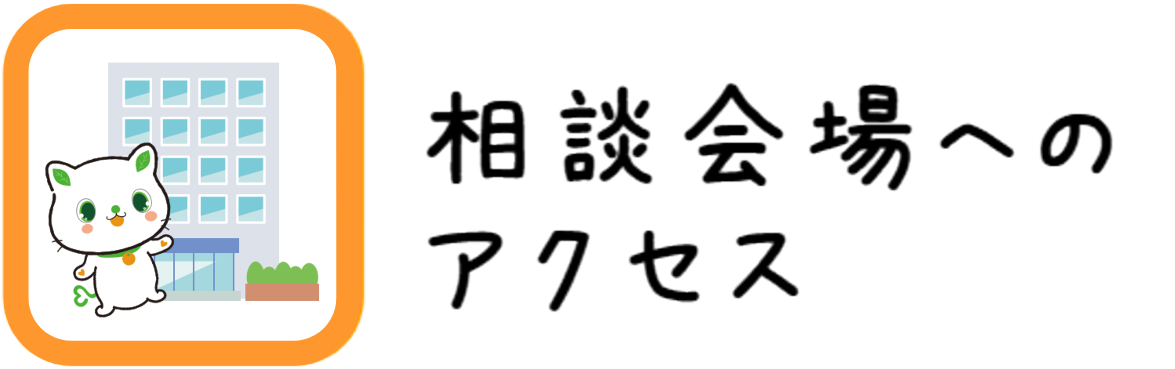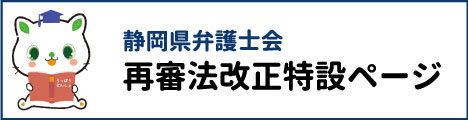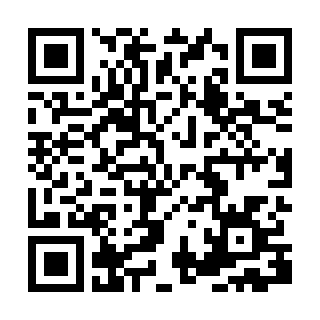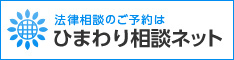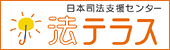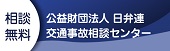1 2024年4月18日、殺人罪、危険運転致死罪などの遺族や性犯罪の被害者を、早期の段階から弁護士が一貫して支援する犯罪被害者等支援弁護士制度(以下「本制度」という。)の創設を盛り込んだ総合法律支援法の一部を改正する法律が成立した。
本制度については、2026年までの運用開始を予定し、現在、その具体的内容について検討が進行しているとのことである。
本制度は、国費によって、犯罪被害が発生した早期の段階から犯罪被害者等に対する弁護士の支援を実現するもので、多くの犯罪被害者等が長年その制度化を求めてきたものであり、当会としても本制度の創設を歓迎し、高く評価する。
2 本制度においては、従来は、資力要件に該当する被害者等であっても、民事法律扶助、犯罪被害者法律援助(委託援助)等の各制度を横断的に利用する必要があった、被害届・告訴状の作成・提出、加害者側との示談交渉、損害賠償請求訴訟、捜査機関、裁判所、行政機関への同行―など犯罪被害者等としてなしうる一連の対応について、本制度の利用によって一括して対応できる点で、有用である。
さらに、弁護士費用の支払いなどで「生活の維持が困難となる恐れ」がある人に限って利用可能とし、利用者には原則として費用負担を求めない点にも特徴がある。
利用者にとってできるだけ経済的負担をさせることがないよう、幅広く利用できるような制度構築が望まれるところである。
3 一方、これを担う弁護士に対しても、有用な制度となる必要がある。
本制度は、上記のように、犯罪被害者等にとって犯罪被害者等としてなし得る一連の対応について一括して対応出来る点で有用であるが、その反面、担い手となる弁護士には従来以上に幅広い対応が求められる。
特に、犯罪被害者の支援は通常の業務と異なり、被害者の心情への配慮、二次被害の防止等といった慎重、広範な対応が要求される。
また、刑事民事の両手続にわたる多様な手続への長期間の関与が求められる。このように、本制度の担い手となる弁護士の業務の重要性は明らかに増大しているのであり、こうした業務の性質に応じた報酬として適切な内容が定められなければならない。
これに対し、民事法律扶助や委託援助などの現行の制度では、いずれも弁護士への報酬がその業務内容に比して低廉に抑えられ、業務量・内容に応じた適切な報酬がない結果、担い手である弁護士にとって過大な負担となっている状況が続いている。
総合法律支援法第2条、第6条及び第8条において、「国の責務」として「総合法律支援の実施及び体制の整備に当たって」「被害者等の援助に関する制度を十分に利用することのできる態勢の充実が図られなければならない」と規定されており、その趣旨からすれば、本制度において弁護士費用が国費で賄われるということは、国が犯罪被害者等を支援する弁護士を積極的にサポートすることを意味しており、費用についても従来の基準を超えた適切な報酬基準によらなければならない。
本制度がいかに有用なものであっても、その担い手である弁護士にとって業務として持続可能な適切な報酬が定められなければ、十分な担い手が確保できず、ひいては被害者等にとって有用な制度にならない可能性が高いのである。
4 適切な報酬の具体的内容については、日本司法支援センターや委託援助の現行の基準を用いるのではなく、例えば、(旧)日弁連報酬基準を参考にして、刑事民事の手続ごとに報酬を算定することが基準として明確であり、業務に対する評価としても適切であると考えられるが、いずれにせよ、制度が予定する広範な手続への対応に応じた報酬が定められることが、本制度の適切な運用にとって不可欠であると思料する。
以上、当会は、犯罪被害者等支援弁護士制度の創設を歓迎しながらも、その制度の内容として担い手である弁護士にとって適切な報酬が定められることを切に求めるものである。
静岡県弁護士会
会長 梅田 欣一
印刷用PDFはこちら


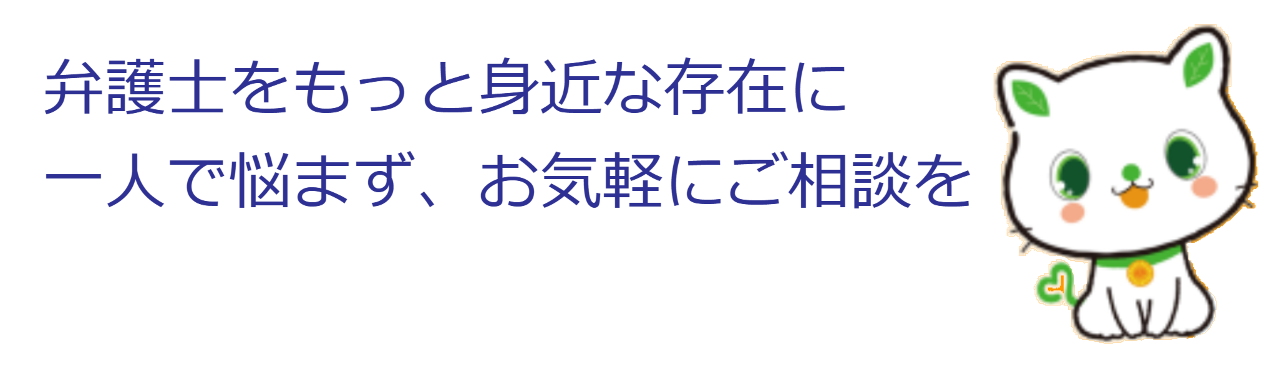
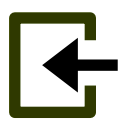 会員専用
会員専用
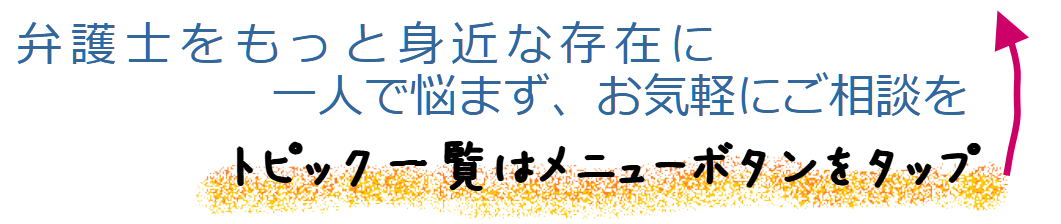

 ツイッター
ツイッター